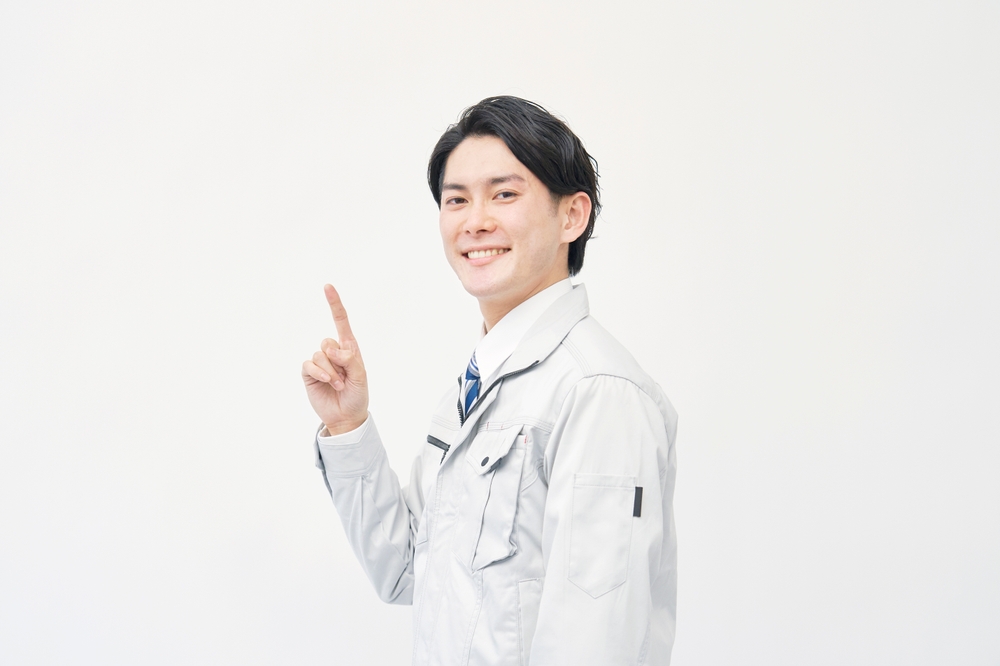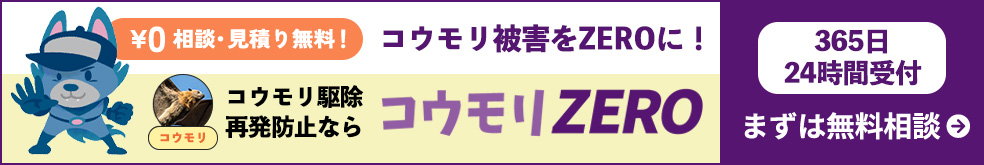目次
コウモリのフンの特徴

コウモリのフンには、独特の特徴があるため、ほかの動物のフンと区別することができます。ここでは、見た目・臭い、場所に分けてコウモリのフンの特徴を紹介します。
見た目・臭い
コウモリのフンは黒色または茶色で、乾燥してパサパサしています。大きさは5mmから1cm程度で、細長くよじれた形状をしています。フンの表面は粉っぽく、崩れやすいことがほとんどです。
臭いは、ドブのような嫌な臭いと酸っぱい臭いが混じっているのが特徴です。見た目だけでなく、臭いからもコウモリのフンであることを確認できます。
特に、乾燥したフンが粉状に崩れている様子やその独特の臭いは、コウモリの存在を示す重要な手がかりとなります。
場所
コウモリのフンは、特定の場所に集中して見られることが多く、主に屋外で見つかります。具体的な場所としては、軒先、ベランダ、屋根の下、雨戸、室外機、換気扇などがあげられます。
このような場所にコウモリのフンが落ちている場合、近くにコウモリが住み着いている可能性が高いです。特に、一箇所にフンがまとまっている場合は、コウモリの巣が近くにあると考えられます。
コウモリは夜間に活動するため、昼間ではなく朝にフンを発見することが多々あります。コウモリのフンを発見した場合は、早急に対策を講じることが重要です。
コウモリの巣が作られやすい場所については、下記の記事で紹介しています。
コウモリの巣が作られやすい場所については、下記の記事で紹介しています。
「コウモリの巣はどこにできる?場所の特徴や見つけた場合の対処法」
コウモリのフンと他の動物の見分け方

コウモリのフンに対して適切に対処するためには、他の動物のフンと見分ける必要があります。では、コウモリのフンと間違えやすい動物のフンとの見分け方を見ていきましょう。
ここでは、ネズミとヤモリのフンの特徴を紹介します。
ネズミのフンの特徴
ネズミのフンの大きさはさまざまで、小さいものだと5mm程度ですが、大きいものは20mm程度もあります。コウモリのフンは5~10mm程度のため、全体的に見ればネズミのフンのほうが大きめです。
色もやや異なります。コウモリのフンは黒っぽい色をしているのに対して、ネズミのフンは焦げ茶色や灰色などです。大きさと色だけだと、見分けるのがやや難しいこともあるかもしれません。
形状や質感などを比べると見分けやすいです。コウモリのフンは、よじれた形状をしていて細長い特徴を持ちますが、ネズミのフンは楕円形で丸みを帯びています。
質感もコウモリのフンはパサパサしていますが、ネズミは果物や穀物を食べるため、フンは密度が高く硬く水分を多く含んでベタベタしているのが特徴です。
ヤモリのフンの特徴
ヤモリのフンは大きさがコウモリのフンと同じくらいで、水分もあまり含んでいません。色も黒色や茶色などのため、コウモリのフンと良く似ています。細長く丸みを帯びた形状をしているため、形状でコウモリのフンと見分けると良いでしょう。
また、ヤモリのフンは端のほうに白い塊があるのも特徴です。この白い塊は尿酸であり、水分をできるだけ体内に保持しようとする働きのためにできるものです。この部分でもコウモリのフンと見分けられます。
コウモリのフンがもたらす被害

コウモリのフンは一見無害に思えるかもしれませんが、実際には人間の健康や住宅にさまざまな被害をもたらす危険性があります。ここでは、コウモリのフンが引き起こす具体的な被害について詳しく解説します。
健康への被害
コウモリのフンには、さまざまな病原菌、ウイルス、寄生虫が含まれているおそれがあります。これらは人間の健康に重大な影響を与えかねません。乾燥したフンは粉々になりやすく、風に乗って空気中に漂うため、吸い込むことで健康被害を引き起こす可能性があるのです。
例えば、コウモリのフンにはヒストプラスマという真菌が含まれていることがあり、吸い込むとヒストプラスマ症という肺の感染症を引き起こすケースがあります。
また、狂犬病ウイルスやリッサウイルスなど、感染症の原因となるウイルスも含まれていることがあります。いずれも発症すると命に関わる場合もあるため注意が必要です。
そのほか、コウモリのフンに含まれるダニやノミなどの寄生虫が人間に寄生することもあります。皮膚炎やその他のアレルギー反応を引き起こす原因となりかねません。特に、喘息やアレルギーを持つ人にとって、コウモリのフンは大きなリスクとなります。
コウモリがもたらす健康被害については、下記について詳しく紹介しています。
「コウモリはどんな病気を持っている?危険な感染症から身を守るには」
住宅への被害
コウモリのフンは、健康への被害だけでなく、住宅にも重大なダメージを与えることがあります。フンを放置したままの状態だと、独特の悪臭が広がるだけでなく、住宅の構造を腐敗させる原因となります。特に天井や壁にフンが溜まると、シミができるだけでなく、長期間放置することで天井が抜け落ちることもあります。
また、コウモリのフンは酸性が強いため、建材を腐食させることがあります。これにより、木材や金属板が劣化し、住宅の強度が低下することがあります。また、フンに含まれる湿気がカビの発生を促進し、住宅の劣化を加速させることになります。
住宅への被害が大きくなると、住環境が悪化するだけでなく、修繕費用が高額になってしまうため早急な対策が必要です。コウモリのフンを見つけた場合は、専門業者に依頼して適切に除去し、再発防止のための対策を講じることが重要です。
コウモリのフンの掃除方法

コウモリのフンが家の周りに落ちているのを見つけたら、すぐに掃除をすることが重要です。前述したように、フンは健康や住宅に悪影響を及ぼすリスクがあります。
ここでは、コウモリのフンを掃除するときに準備するものと掃除方法について紹介します。
準備するもの
コウモリのフンを掃除する前に、下記の用具を準備しましょう。
・ゴム手袋
・マスク(防塵マスクが望ましい)
・ビニール袋
・消毒用アルコールスプレー
・使い捨ての雑巾やペーパータオル
・ほうき
・ちりとり
掃除方法
ここでは、コウモリのフンを掃除する際の流れを紹介します。
【手順】
1.ゴム手袋とマスクを着用して、直接フンに触れないように準備する
2.ビニール袋を二重にして、ほうきとちりとりでフンを慎重に拾い集める
3.拾い集めたフンをビニール袋に入れ、処分する
4.フンを取り除いた後、残った場所を消毒用アルコールスプレーでしっかりと消毒する
5.消毒後はしばらく放置して、アルコールが完全に乾燥するのを待つ
掃除に使用したゴム手袋やマスク、雑巾、ほうき、ちりとりには病原菌やウイルスが付いている可能性があるため、ゴミ袋に入れて処分することをおすすめします。
このように、適切な掃除と消毒を行うことで、コウモリのフンによる健康リスクを最小限に抑えることができます。家の周りにフンが見つかった場合は、迅速に対処することを心がけましょう。
コウモリのフンに触ってしまった場合の対処法

コウモリのフンを発見した際などに、コウモリとは知らず、誤って素手で触ってしまうこともあるでしょう。その際はすぐに手を洗う必要があります。石けんやハンドソープなどを使用して泡立て、20秒以上かけて丁寧に洗い、流水で流しましょう。
手洗いが不十分だと、コウモリのフンに含まれる病原菌やウイルスなどが残ってしまう可能性があります。普段の手洗いよりも念入りに行うことが重要です。
手洗いをした後は、アルコール消毒液を使用して手全体を消毒しましょう。指の間や爪の周りなどにも消毒液を付けて擦り込みます。
コウモリのフンに触れた箇所の付近に、傷がある場合、注意が必要です。傷口から、病原菌やウイルスがそこから体内に侵入してしまうおそれがあります。不安な場合には医師に相談するのが望ましいです。
また、手洗いをするまでは、雑貨や衣服などには極力触れないようにしましょう。手洗いをする前に、何かに触れてしまうと、触れた箇所の消毒もしなければなりません。
コウモリの侵入を防ぐ方法
コウモリの侵入を防ぐことは、フンによる被害を防止するために重要です。ここではコウモリの侵入を防ぐための効果的な方法を紹介します。
忌避剤を使う
忌避剤を使うことで、コウモリを追い出し、寄せ付けなくすることができます。コウモリは鳥獣保護管理法で守られているため、捕獲や殺傷は禁止されています。忌避剤であれば、コウモリを殺傷することなく駆除できるため、安心です。
燻煙剤タイプやスプレータイプは、コウモリを追い出す際におすすめです。使用することで、コウモリが居心地の悪い環境を作り出すことができます。ジェルタイプの忌避剤を置いておくことで、そもそもコウモリが寄り付かない環境を維持することが可能です。
ただし、忌避剤が効かない場合もあるため、ほかの方法を併用することも検討してください。
住宅をこまめにメンテナンスする
住宅の点検やメンテナンスも、コウモリの侵入を防止するための対策として効果的です。古い住宅だと、コウモリが侵入しそうな穴や隙間が多くあります。外から住宅全体を見渡してみて、穴や隙間がないかどうかチェックしておきましょう。もし見つかったら、早めに修理しておくのが望ましいです。
また、雨戸や車庫のシャッターなどをほとんど開け閉めしないでおくのは良くありません。人があまり出入りせず暗いため、コウモリから快適な場所だと認識されてしまいます。
そのため、雨戸やシャッターはできるだけ頻繁に開け閉めするようにしましょう。日光が差し込んだり人が出入りしたりすると、コウモリは棲みにくい場所だと認識します。それとあわせて、家の周りを掃除して清潔に保つことも重要です。
コウモリが棲み着きやすい家の特徴については、下記の記事で紹介しています。
「コウモリに好かれる家に共通する特徴は?寄せ付けない方法も解説」
侵入経路を塞ぐ
コウモリの侵入を防ぐためには、まず侵入経路を特定し、塞ぐことが重要です。コウモリはわずか1cmほどの隙間でも侵入できるため注意が必要です。
対策を講じる際は、下記の場所をチェックして侵入経路になり得ないか確認しましょう。
・室外機の配管の隙間
・通気口や換気口
・屋根と壁の隙間
・雨戸の戸袋
確認してフンが落ちている場所を特定することで、侵入経路を見つける手助けになります。侵入経路を見つけたら、金網やシーリング材、防鳥ネットなどを使ってしっかりと塞ぎましょう。
コウモリの侵入を防ぐためには、忌避剤の使用と侵入経路の封鎖を組み合わせて行うことが有効です。
まとめ
コウモリのフンには病原菌や寄生虫が含まれており、吸い込むと健康被害を引き起こすおそれがあります。また、フンが住宅の構造を腐食させることもあり、修繕費が高額になることもあります。
独特の見た目と臭いで発見しやすいので、発見した場合はすぐに掃除と消毒を行い、侵入経路をしっかりと封鎖することが重要です。
ご自身でフンの掃除やコウモリの侵入対策をするのが難しい場合は、プロの駆除サービスを活用するのも有効な手段です。まずは専門家に相談し、安全な環境を確保しましょう。
「がいじゅうZERO」なら、害獣駆除のプロによって確実にコウモリを退治することが可能です。ご相談から調査・見積り、駆除作業までワンストップで対応しているため、スピーディーに駆除できます。再発防止策も徹底しており、最長10年以上の保証を付けております。
相談・見積もりは無料なため、まずはお気軽にお問い合わせください。
※フンの清掃や消毒は、屋内の被害であれば対応可能です。屋外でのフンは対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。