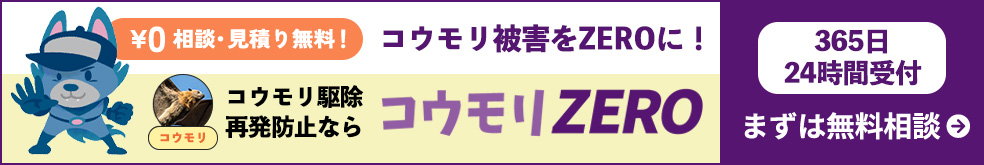目次
コウモリが壁にとまっている理由

自宅の壁にコウモリがとまっているのを発見すると、多くの方が驚かれることでしょう。コウモリが壁にとまる行動には、明確な理由があります。
コウモリには、「ナイトルースト」と呼ばれる場所に、夜間に一時的に休憩する習性があります。これは長時間の飛行の合間に体力を回復させる重要な行動で、安全で風雨をしのげる場所を選んで休息を取ります。
さらに注意が必要なのは、壁から長時間動かないコウモリの存在です。これは単なる休憩ではなく、そこを巣として利用しようと考えている可能性が高いサインです。コウモリは一度気に入った場所を見つけると、そこに定住しようとする習性があります。
特に春から秋にかけての繁殖期や冬眠前の時期には、このような行動が顕著に見られます。壁の隙間や軒下など、外敵から身を守れる場所を探し回っているのです。
コウモリが壁にとまっているときに注意すべき被害1:住宅被害

コウモリが家に侵入すると、深刻な住宅被害が発生する可能性があります。
糞尿被害
コウモリによる最も深刻な被害のひとつが糞尿被害です。コウモリの糞尿は単に悪臭を放つだけではありません。壁や天井に付着した糞尿は、時間が経つにつれて建材を腐食させ、住宅の構造にまで悪影響を及ぼします。
特に木造住宅の場合、糞尿に含まれる酸性成分が木材を徐々に傷めていきます。また、糞尿が乾燥すると粉塵となって空気中に舞い上がり、住環境の悪化につながります。天井裏に侵入されてしまった場合、糞尿が天井板にシミを作り、最終的には張り替えが必要になるケースも少なくありません。
さらに、コウモリの糞は乾燥すると非常に軽くなり、風に乗って家中に拡散してしまいます。これにより、家全体が不衛生な状態になってしまうおそれがあります。
巣作り被害
コウモリが巣作りを始めると、住宅への被害はさらに深刻になります。巣を作る際に、電気配線や断熱材を傷つけることが頻繁に起こります。特に電気配線が損傷を受けると、漏電や火災の原因となる危険性があります。
コウモリは巣材として木の枝、葉っぱ、毛皮などの可燃性の材料を使用します。これらの材料が電気配線の近くに蓄積されると、火災のリスクが格段に高まります。実際に、コウモリの巣が原因で住宅火災が発生した事例も報告されています。
さらに深刻な問題は、コウモリの繁殖サイクルです。一度繁殖に成功すると、その子孫も同じ場所に住み続ける習性があります。つまり、一匹のコウモリを放置すると、数年後には複数のコウモリが棲み着く「コウモリ一家」が形成されてしまうのです。
このような繁殖被害により、コウモリの数が年々増加し、それに比例して住宅被害も拡大します。そのため早期対策が重要なのです。
コウモリが壁にとまっているときに注意すべき被害2:健康被害
コウモリによる被害でより深刻なのは、私たち人間の健康に直接影響を与える健康被害です。なぜなら、コウモリはさまざまな病原菌を保有している可能性があり、人が接触することで病気に感染してしまう危険があるからです。
騒音による寝不足
コウモリは夜行性の動物のため、私たちが眠りについた深夜から明け方にかけて最も活発に活動します。天井裏や壁の中で「バタバタ」と飛び回る音や、「キーキー」という甲高い鳴き声が夜通し続くことがあります。
この騒音は想像以上に大きく、特に静かな夜間では非常に気になるレベルです。継続的な睡眠妨害により、日中の集中力低下、イライラ、体調不良などの症状が現れることがあります。
また、コウモリの活動音に対する不安やストレスが蓄積され、精神的な健康にも悪影響を与えます。特に小さなお子様がいるご家庭では、夜鳴きや夜驚症の原因となることもあります。
アレルギー症状
コウモリの身体には多数のノミやダニが付着しています。これらの寄生虫はコウモリが棲み着いた場所周辺に拡散し、人間にも被害をもたらします。
特にダニによるアレルギー症状は深刻で、皮膚のかゆみ、発疹、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどの症状が現れます。すでにアレルギー体質の方や小さなお子様、高齢者の方は、より重篤な症状が出る可能性があります。
さらに、コウモリの毛や皮膚の断片も空気中に舞い上がり、これらがアレルゲンとして呼吸器系のトラブルを引き起こすことがあります。
感染症
最も深刻な健康被害は、コウモリが媒介する各種感染症です。コウモリは以下のような危険な病気の感染源となる可能性があります。
サルモネラ症は、発熱、下痢、嘔吐などの症状を引き起こす食中毒の原因となります。
日本国内での発症例は報告されていないものの、海外では狂犬病に似た症状を示すリッサウイルス感染症や、ニパウイルス感染症、エボラ出血熱、ヘンドラウイルス感染症など、致死率の高い感染症にコウモリは関与しています。
特に免疫力の低下している方や持病をお持ちの方は、感染症にかかるリスクが高くなります。コウモリを発見した際は、絶対に素手で触らず、適切な対処が必要です。
コウモリが媒介する病気については、こちらの記事もご覧ください。
「コウモリはどんな病気を持っている?危険な感染症から身を守るには」
【注意】コウモリは勝手に駆除できない!

コウモリによる被害を受けていても、個人が勝手にコウモリを駆除することは法律で禁止されています。コウモリは鳥獣保護法の対象動物に指定されており、許可なく殺傷や捕獲を行った場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
この法律は、生態系のバランスを保つために制定され、コウモリも重要な役割を果たす野生動物として保護されています。たとえ自宅に被害を与えているコウモリであっても、法的な手続きを踏まずに駆除することは犯罪行為となります。
ただし、コウモリを傷つけずに追い払うことは認められています。重要なのは「殺傷・捕獲」をしないことであり、忌避剤や音響機器を使って棲み着かないようにする対策は問題ありません。
このような法的制約があるからこそ、コウモリ問題は専門知識を持った業者に相談するのが最も安全で確実な解決方法となります。
コウモリを見つけたときにできることや、してはいけないことなどについては、こちらの記事も参考にしてください。
「コウモリも鳥獣保護法で守られている?コウモリを見つけたときの対処法を解説」
コウモリが壁にとまっているときの対策
ここでは、法律を守りながら、コウモリを傷つけることなく追い払う方法を紹介します。これらの対策を組み合わせることで、効果的にコウモリを遠ざけることができます。
コウモリを追い出す
以下に、コウモリを追い出すためにできる簡単な対策を2つ紹介します。
忌避剤を使う
忌避剤を使用する方法は、最も手軽で効果的な対策のひとつです。
市販されているコウモリ用忌避剤には、コウモリが嫌う臭いの成分が含まれており、スプレータイプや設置タイプなどさまざまな種類があります。
ハッカ油やナフタリンなど、家庭にある物でも代用できますが、専用の忌避剤のほうが効果は高いとされています。
超音波を発する機器
超音波も効果的です。コウモリは超音波を使って周囲の状況を把握するため、人工的な超音波によって混乱を与え、居心地の悪さを感じさせることができます。ソーラー式や電池式の超音波発生器が市販されており、設置も比較的簡単です。
ただし、これらの方法は一時的な効果に留まることが多く、コウモリが慣れてしまうと再び戻ってくる可能性があります。継続的な使用と他の対策との併用が重要です。
侵入口を塞ぐ
コウモリの侵入を根本的に防ぐためには、侵入口を物理的に塞ぐことが最も確実です。コウモリは直径1~2cmほどの小さな穴があれば侵入できるため、住宅の隙間を徹底的にチェックする必要があります。
よくある侵入口は、屋根と外壁の接合部、軒天の隙間、換気口周辺、エアコンの配管穴などです。これらの場所をシーリング材で埋めたり、金網やパンチングメタルで覆ったりすることで侵入を防げます。
ただし、侵入口を塞ぐ作業は、コウモリが中にいないことを確認してから行う必要があります。コウモリを閉じ込めてしまうと、中で死んでしまい、より深刻な問題を引き起こす可能性があります。
専門業者に依頼する
最も確実で安全な解決方法は、専門業者に依頼することです。プロの業者であれば、法律を遵守しながら迅速かつ確実に駆除対応を行ってくれます。
コウモリ駆除なら、「がいじゅうZERO」にご相談ください。ご相談から調査見積り、駆除作業まで自社でワンストップで承りますので、スピーディーな駆除が実現します。
施工後は、消毒・修繕・清掃も徹底的に行います。さらに最長10年間の保証付きで、アフターケアも万全です。
コウモリによる被害にお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
コウモリが壁にとまるのは休憩や巣作りのためで、放置すると糞尿や巣作りによる住宅被害、騒音・アレルギー・感染症などの深刻な健康被害が発生します。個人での駆除は法律で禁止されているため、忌避剤や侵入口の封鎖で一時対策を行い、根本解決には専門業者への依頼が最も確実です。早めの対策で安心な住環境を守りましょう。