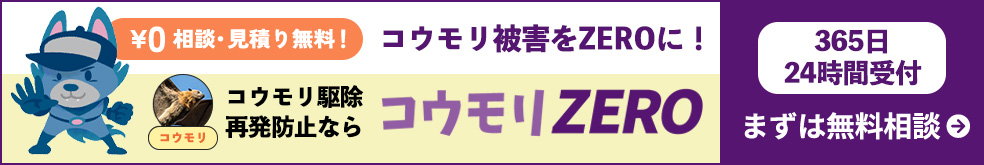コウモリはどういう所に棲み着く?

コウモリは夜行性の哺乳類で、昼間は身を隠せる、暗く静かな場所を好みます。最近では都市部の住宅に棲み着くケースが増えており、気づかないうちに家の一部に巣を形成していることがあります。
コウモリが棲み着いてしまうと、後述するようにさまざまな被害が発生するため、棲み着きやすい場所や家の特徴を知ることが対策の第一歩となります。
コウモリが棲み着きやすい家の場所
コウモリは住宅のいろいろな場所に棲み着く傾向があります。もっとも多いのは屋根裏や天井裏で、人目につきにくく、外敵から身を守れる安全な場所となっています。また、屋根の瓦の隙間も好まれる場所のひとつで、特に古い家屋では瓦のズレなどから侵入しやすくなっています。
軒下や雨戸の隙間も要注意です。コウモリは体が小さいため、わずか1~2cm程度の隙間さえあれば侵入可能です。換気口の中や壁の中といった普段目にすることのない場所にも棲み着くことがあります。
さらに、エアコン室外機の隙間や配管、給湯器の隙間、ダクトなども格好の住処となります。これらの場所は外部と家の内部をつなぐ通路となり、コウモリが行き来しやすい環境を作り出しています。
コウモリが棲み着きやすい家の特徴
ここでは、コウモリが棲み着きやすい家の特徴を4つ紹介します。
雨風がしのげて暖かい
コウモリは体温調節が難しい生き物のため、雨風を避け、適度な温度が保たれる環境を好みます。特に住宅の屋根裏や壁の中は、外部からの気温変化の影響を受けにくく、安定した温かい環境となるため好まれます。また、日当たりの良い南向きの場所は、冬場でも比較的温かく保たれるため、棲み着きやすい傾向にあります。
侵入できる隙間がある
コウモリは体が小さく柔軟なため、非常に狭い隙間からでも侵入できます。古い家屋や経年劣化によって生じた壁のヒビ、屋根の隙間、換気口のすき間などは、絶好の侵入経路となります。定期的な家のメンテナンスを怠ると、これらの隙間から侵入されるリスクが高まります。
ぶら下がれる場所がある
コウモリは休息時に頭を下にしてぶら下がる習性があります。そのため、屋根裏の梁や軒下など、ぶら下がれるスペースがある場所を特に好みます。こうした場所は身を守りやすく、安全に休息できる環境となっています。
餌が集まる場所が近くにある
コウモリは、主に昆虫を餌としているため、蛾や蚊などが多く集まる場所の近くに住処を構える傾向があります。家の周りに街灯があったり、水辺が近かったりすると、昆虫が集まりやすく、コウモリにとって餌場として理想的な環境となります。
そのため、このような条件が揃った住宅は特に注意が必要です。
コウモリが家に棲み着いた場合の被害

コウモリが家に棲み着くと、生活環境にさまざまな悪影響を及ぼします。騒音や感染症のリスク、糞尿による被害など、放置すればするほど問題は大きくなっていきます。
これらの被害を理解し、早期に対策を講じることが重要です。
騒音の被害
コウモリが家に棲み着くと、まず悩まされるのが騒音問題です。コウモリ特有の高周波の鳴き声や、羽ばたく音が家の中に響き渡ります。特に困るのは、コウモリが夜行性である点です。人間が眠りにつく夕方から夜中にかけてが、コウモリのもっとも活発な活動時間となります。
さらに厄介なのは、コウモリの繁殖力の強さです。発見が遅れると、気づかないうちに数十羽から百匹近くまで増えていることもあります。これだけの数になると、その騒音は相当なもので、夜間の安眠を妨げる深刻な問題となります。特に繁殖期には鳴き声も頻繁になり、騒音被害はピークに達します。
感染症のリスク
コウモリはさまざまな場所を飛び回るため、多くの病原菌や寄生虫を保有している可能性があります。万が一触れたり噛まれたりすると、感染症にかかるリスクがあるため、直接接触は避けるべきです。
また、コウモリの体には、ダニやノミなどの寄生虫が付着している可能性も高いため、死骸やフンに対しても素手で触れないように注意が必要です。
特に子どもやペットがいる家庭では、コウモリとの接触による感染症リスクは深刻に受け止めるべき問題です。コウモリを見つけた場合は、決して素手で捕まえようとせず、専門家に相談することをおすすめします。
コウモリに噛まれた場合については、下記の記事もご覧ください。
「コウモリに噛まれたらどうする?素早く正しい対処を! 」
糞尿の被害
コウモリが棲み着くと避けられないのが、糞尿による被害です。コウモリの巣が形成されると、棲み着いた場所には、大量の糞尿が蓄積されていきます。このフンからは強い悪臭が発生し、生活環境を著しく悪化させます。
さらに、フンはゴキブリやハエ、ダニやノミなどの二次的な害虫を呼び寄せる原因にもなります。つまり、コウモリの糞尿被害は、別の害虫問題を引き起こす連鎖反応を生み出すのです。
木造住宅の屋根裏に棲み着いた場合は特に注意が必要です。糞尿が長期間にわたって蓄積されると、その成分が天井材を浸食し、やがて天井にシミとなって表れることがあります。このような状態になると、家の資産価値の低下にもつながるため、早期発見・早期対策が重要です。
フン対策については、こちらで詳しく解説しています。
「【コウモリ】フン対策はどうすれば良い?特徴や被害についても解説」
家に棲み着いたコウモリを駆除する方法

コウモリの駆除には法的制限があり、対処方法を誤ると思わぬトラブルを招くことがあります。自分でできる対策と、専門業者への依頼の両面から、効果的な解決法を見ていきましょう。
自分で行う方法
まず重要なのは、コウモリを自分で勝手に駆除してはならないということです。コウモリは鳥獣保護法によって保護されている動物であるため、許可なく捕獲や殺傷をすることは法律違反となります。違反した場合、罰則の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
そのため、自分でできるのは「駆除」ではなく「追い出し」や「予防」の対策となります。自分でできるコウモリ対策は次の通りです。
忌避剤を使う方法は比較的簡単で効果的です。コウモリは特定のにおいを嫌う習性があり、市販のコウモリ用忌避剤やナフタリン、香辛料などを利用することで、コウモリを遠ざけることができます。ただし、効果は一時的なので、定期的な使用が必要です。
侵入経路を断つことも重要です。コウモリが出入りしている隙間を特定し、コウモリが不在の時間帯(日中の活動時)に金網や網戸、コーキング材などで塞ぎます。ただし、中にコウモリが残っていないことを確認してからふさぐようにしましょう。
また、コウモリが寄り付かない環境作りも効果的です。虫を寄せ付けにくいLED照明に変更する、庭の昆虫を減らすなど、コウモリの餌となる虫が集まりにくい環境を整えることで、自然と寄り付かなくなります。
自分で行いたいと考えている場合は、こちらの記事もご覧ください。
「コウモリは駆除してはいけない!正しい対処法について徹底解説」
専門業者に依頼する
コウモリの棲み着く場所は、屋根や軒下などの高所が多く、素人が安全に作業することは困難な場合があります。また前述の通り、駆除までを自分で行うことは法律上できません。確実かつ安全に対処するには、害獣駆除の専門業者に依頼するのがおすすめです。
専門業者は適切な許可を持っており、コウモリを傷つけることなく安全に追い出す技術と経験を持っています。また、侵入経路の特定や再発防止策の提案など、根本的な解決策を提供してくれます。
コウモリを駆除するなら、「がいじゅうZERO」にお任せください。相談・調査・見積もりから駆除作業まで、自社内でワンストップ対応しており、調査と駆除作業を同じスタッフが行うため、状況を正確に把握した上での対策が可能です。
また、駆除後の清掃・消毒や再発防止対策も徹底しており、コウモリ問題を根本から解決できます。コウモリの被害にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
コウモリは夜行性哺乳類で、暗く静かな場所を住処とし、近年は都市部の住宅にも棲み着くようになっています。屋根裏や天井裏、瓦の隙間、軒下、壁の中など、わずか1~2cm程度の隙間からも侵入可能です。
特に雨風がしのげて暖かい場所、ぶら下がれるスペースがある場所、餌となる昆虫が多い環境を好みます。
棲み着くと、騒音や感染症リスク、糞尿による悪臭や二次害虫の発生などの被害が生じます。駆除には法的制限があるため、忌避剤の使用や侵入経路を塞ぐなどの対策を自分で行うか、専門業者に依頼するのが安心かつ確実です。
お住まいの環境を定期的にチェックし、小さな隙間も見逃さないようにすることで、コウモリの侵入を未然に防ぎ、快適な住環境を維持しましょう。